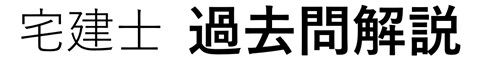ページ
カテゴリーごとの投稿
- カテゴリー: 令和6年(2024)
- 【問50】建物の構造に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
- 【問49】土地に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
- 【問48】次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 【問47】宅地建物取引業者が行う広告に関する次の記述のうち、不当景品類及び不当表示防止法(不動産の表示に関する公正競争規約を含む。)の規定によれば、正しいものはどれか。
- 【問46】独立行政法人住宅金融支援機構(以下この問において「機構」という。)に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- 【問45】特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律に基づく住宅販売瑕疵担保保証金(以下この問において「保証金」という。)の供託又は住宅販売瑕疵担保責任保険契約(以下この問において「保険契約」という。)の締結に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 【問44】宅地建物取引業者Aが宅地建物取引業法第 37 条の規定により交付すべき書面(以下この問において「37 条書面」という。)に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定に違反しないものはどれか。
- 【問43】宅地建物取引士の登録及び宅地建物取引士証に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- 【問42】次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定及び「宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン」によれば、誤っているものはどれか。
- 【問41】宅地建物取引業者が行う宅地建物取引業法第 35 条に規定する重要事項の説明に関する次の記述のうち、正しいものはいくつあるか。なお、説明の相手方は宅地建物取引業者ではないものとする。
- 【問40】宅地建物取引業者が媒介により既存建物の貸借の契約を成立させた場合、宅地建物取引業法第 37 条の規定により当該貸借の契約当事者に対して交付すべき書面に必ず記載しなければならない事項の組合せとして正しいものは次の 1 から 4 のうちどれか。
- 【問39】宅地建物取引業法第 50 条第 2 項の届出をすべき場所に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。なお、これらの場所では、宅地若しくは建物の売買若しくは交換の契約(予約を含む。)若しくは宅地若しくは建物の売買、交換若しくは貸借の代理若しくは媒介の契約を締結し、又はこれらの契約の申込みを受けるものとする。
- 【問38】宅地建物取引業の免許(以下この問において「免許」という。)に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。
- 【問37】宅地建物取引業者が行う宅地建物取引業法第 35 条に規定する重要事項説明に関する次の記述のうち、正しいものはいくつあるか。なお、説明の相手方は宅地建物取引業者ではないものとする。
- 【問36】営業保証金及び宅地建物取引業保証協会(以下この問において「保証協会」という。)に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、誤っているものはどれか。
- 【問35】宅地建物取引業者Aが宅地建物取引業法第37条の規定により交付すべき書面(以下この問において「37条書面」という。)に記載すべき事項を電磁的方法により提供すること(以下この問において「37条書面の電磁的方法による提供」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 【問34】宅地建物取引業者Aが、自ら売主として、宅地建物取引業者ではない個人Bとの間で、土地付建物を4,000万円で売却する売買契約(所有権の登記は当該土地付建物の引渡し時に行うものとする。)を締結する場合における宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)第41条又は第41条の2の規定に基づく手付金等の保全措置(以下この問において「保全措置」という。)に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- 【問33】宅地建物取引業者がその業務に関して行う広告に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、誤っているものはどれか。
- 【問32】宅地建物取引業者Aが、BからB所有の中古住宅の売却の依頼を受け、Bと専任媒介契約(専属専任媒介契約ではないものとする。)を締結した。この場合における次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、正しいものはどれか。
- 【問31】次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、正しいものはどれか。
- 【問30】宅地建物取引業者Aが、自ら売主として、宅地建物取引業者ではない個人Bとの間で宅地の売買契約を締結し、手付金を支払ったBが、宅地建物取引業法第37条の2の規定に基づくいわゆるクーリング・オフにより、当該売買契約を契約締結の日の翌日に解除しようとしている。この場合に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- 【問29】宅地建物取引士に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、正しいものはどれか。
- 【問28】宅地建物取引業者A(消費税課税事業者)及び宅地建物取引業者B(消費税免税事業者)が受領した報酬に関するアからウの記述のうち、宅地建物取引業法の規定に違反しないものの組合せは1から4のうちどれか。なお、代理、媒介に当たり、広告の依頼は行われていないものとする。
- 【問27】宅地建物取引業者Aに関する次の記述のうち、正しいものはどれか。なお、Aは宅地建物取引業保証協会の社員ではないものとする。
- 【問26】宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明に関する次の記述のうち、正しいものはいくつあるか。なお、説明の相手方は宅地建物取引業者ではないものとする。
- 【問25】不動産の鑑定評価に関する次の記述のうち、不動産鑑定評価基準によれば、誤っているものはどれか。
- 【問24】不動産取得税に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 【問23】住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除(以下この問において「住宅ローン控除」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。なお、以下の居住用家屋は、令和5年に建築基準法第6条第1項の確認(建築確認)を受けたものとする。
- 【問22】国土利用計画法(以下この問において「法」という。)第23条の届出(以下この問において「事後届出」という。)及び法第27条の7の監視区域内の届出(以下この問において「事前届出」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。なお、この問において「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市にあってはその長をいうものとする。
- 【問21】農地に関する次の記述のうち、農地法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、誤っているものはどれか。
- 【問20】土地区画整理法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。なお、この問において、同法第136条の3による大都市等の特例及び条例で定める事務処理の特例は考慮しないものとする。
- 【問19】宅地造成及び特定盛土等規制法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。なお、この問において「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市及び中核市にあってはその長をいうものとし、地方自治法に基づく施行時特例市に係る経過措置については考慮しないものとする。
- 【問18】次の記述のうち、建築基準法の規定によれば、正しいものはどれか。
- 【問17】建築基準法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。なお、建築副主事の確認にあっては、建築基準法に定める大規模建築物以外の建築物に限るものとする。
- 【問16】都市計画法(以下この問において「法」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。ただし、この問において条例による特別の定めはないものとし、「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市及び施行時特例市にあってはその長をいうものとする。
- 【問15】都市計画法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- 【問14】不動産の登記に関する次の記述のうち、不動産登記法の規定によれば、誤っているものはどれか。
- 【問13】建物の区分所有等に関する法律に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- 【問12】賃貸人Aと賃借人Bとが、居住目的で期間を3年として、借地借家法第38条の定期建物賃貸借契約(以下この問において「契約①」という。)を締結した場合と、定期建物賃貸借契約でも一時使用目的の賃貸借契約でもない普通建物賃貸借契約(以下この問において「契約②」という。)を締結した場合とに関する次の記述のうち、借地借家法の規定によれば、正しいものはどれか。
- 【問11】建物の所有を目的とする土地の賃貸借契約(一時使用目的の借地契約を除く。)に関する次の記述のうち、借地借家法の規定によれば、正しいものはどれか。
- 【問10】売買契約の目的物が品質に関して契約の内容に適合しない場合において、当該契約不適合が売主及び買主のいずれの責めにも帰することができない事由によるものであるとき、履行の追完請求権、代金の減額請求権、損害賠償請求権及び契約の解除権のうち、民法の規定によれば、買主が行使することができない権利のみを掲げたものとして正しいものは次の記述のうちどれか。なお、上記帰責性以外の点について、権利の行使を妨げる事情はないものとする。
- 【問9】承諾に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。
- 【問8】次の記述のうち、民法の条文として規定されていないものはどれか。
- 【問7】Aを貸主、Bを借主として甲建物の賃貸借契約(以下この問において「本件契約」という。)が締結され、Bが甲建物の引渡しを受けた場合における次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。
- 【問6】Aの所有する甲土地にBを地上権者とする地上権(以下この問において「本件地上権」という。)が設定され、その旨の登記がされた後に、甲土地にCを抵当権者とする抵当権が設定され、その旨の登記がされた場合における次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはいくつあるか。
- 【問5】履行遅滞に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。
- 【問4】Aを売主、Bを買主として甲土地の売買契約(以下この問において「本件契約」という。)が締結された直後にAが死亡し、CがAを単独相続した場合における次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。
- 【問3】甲土地につき、A、B、C、Dの 4 人がそれぞれ 4 分の 1 の共有持分を有していて、A、B、CのいずれもDの所在を知ることができない場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。なお、Dの共有持分は、相続財産には属していないものとする。
- 【問2】委任契約・準委任契約に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。
- 【問1】法律行為に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。
- カテゴリー: 令和5年(2023)
- 【問50】建物の構造と材料に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
- 【問49】土地に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
- 【問48】次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- 【問47】宅地建物取引業者が行う広告に関する次の記述のうち、不当景品類及び不当表示防止法(不動産の表示に関する公正競争規約を含む。)の規定によれば、正しいものはどれか。
- 【問46】独立行政法人住宅金融支援機構(以下この問において「機構」という。)に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- 【問45】宅地建物取引業者Aが、自ら売主として、宅地建物取引業者ではない買主Bに新築住宅を販売する場合に関する次の記述のうち、特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律の規定によれば、正しいものはどれか。
- 【問44】宅地建物取引業保証協会(以下この問において「保証協会」という。)に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。
- 【問43】宅地建物取引業者Aが媒介により宅地の売買契約を成立させた場合における宅地建物取引業法第 37 条の規定により交付すべき書面(以下この問において「37 条書面」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 【問42】宅地建物取引業法第 35 条に規定する重要事項の説明に関する次の記述のうち、誤っているものはいくつあるか。
- 【問41】次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。
- 【問40】宅地建物取引業者Aが、BからB所有の中古住宅の売却の依頼を受け、専任媒介契約(専属専任媒介契約ではないものとする。)を締結した場合に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、正しいものはどれか。
- 【問39】宅地建物取引業者Aが、自ら売主として、宅地建物取引業者ではない個人Bとの間で宅地の売買契約を締結する場合における手付金の保全措置に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。なお、当該契約に係る手付金は保全措置が必要なものとする。
- 【問38】次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはいくつあるか。
- 【問37】次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。
- 【問36】次の記述のうち、宅地建物取引業者Aが行う業務に関して宅地建物取引業法の規定に違反するものはいくつあるか。
- 【問35】宅地建物取引業者Aが、自ら売主として、宅地建物取引業者ではない買主Bから宅地の買受けの申込みを受けた場合における宅地建物取引業法第 37 条の 2 の規定に基づくいわゆるクーリング・オフに関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 【問34】宅地建物取引業者A(消費税課税事業者)は貸主Bから建物の貸借の媒介の依頼を受け、宅地建物取引業者C(消費税課税事業者)は借主Dから建物の貸借の媒介の依頼を受け、BとDとの間で、 1 か月分の借賃を 12 万円(消費税等相当額を含まない。)とする賃貸借契約(以下この問において「本件契約」という。)を成立させた場合における次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定に違反するものはいくつあるか。
- 【問33】宅地建物取引業法第 35 条に規定する重要事項の説明に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 【問32】宅地建物取引業者が行う届出に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、誤っているものはどれか。
- 【問31】宅地建物取引業者がその業務に関して行う広告に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、正しいものはどれか。なお、この問において「建築確認」とは、建築基準法第 6 条第 1 項の確認をいうものとする。
- 【問30】宅地建物取引業者A(甲県知事免許)の営業保証金に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはいくつあるか。なお、Aは宅地建物取引業保証協会の社員ではないものとする。
- 【問29】宅地建物取引業の免許(以下この問において「免許」という。)に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。
- 【問28】宅地建物取引業者Aの業務に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定に違反するものはいくつあるか。
- 【問27】宅地建物取引業法第 34 条の 2第1項第4号に規定する建物状況調査(以下この問において「建物状況調査」という。)に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- 【問26】宅地建物取引業法第 37 条の規定により交付すべき書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供すること(以下この問において「37 条書面の電磁的方法による提供」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはいくつあるか。
- 【問25】不動産の鑑定評価に関する次の記述のうち、不動産鑑定評価基準によれば、正しいものはどれか。
- 【問24】不動産取得税に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 【問23】印紙税に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。なお、以下の契約書はいずれも書面により作成されたものとする。
- 【問22】土地を取得する場合における届出に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。なお、この問において「事後届出」とは、国土利用計画法第23条の届出をいい、「重要土地等調査法」とは、重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律をいうものとする。
- 【問21】農地に関する次の記述のうち、農地法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、誤っているものはどれか。
- 【問20】土地区画整理法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- 【問19】宅地造成等規制法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。なお、この問において「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市及び施行時特例市にあってはその長をいうものとする。
- 【問18】次の記述のうち、建築基準法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、正しいものはどれか。
- 【問17】建築基準法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- 【問16】都市計画法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。ただし、この問において条例による特別の定めはないものとし、「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市及び施行時特例市にあってはその長をいうものとする。
- 【問15】都市計画法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 【問14】不動産の登記に関する次の記述のうち、不動産登記法の規定によれば、誤っているものはどれか。
- 【問13】建物の区分所有等に関する法律(以下この問において「法」という。)に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- 【問12】令和5年7月1日に締結された建物の賃貸借契約(定期建物賃貸借契約及び一時使用目的の建物の賃貸借契約を除く。)に関する次の記述のうち、民法及び借地借家法の規定並びに判例によれば、正しいものはどれか。
- 【問11】AがBとの間で、A所有の甲土地につき建物所有目的で期間を 50 年とする賃貸借契約(以下この問において「本件契約」という。)を締結する場合に関する次の記述のうち、借地借家法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。
- 【問10】債務者Aが所有する甲土地には、債権者Bが一番抵当権(債権額 1,000 万円)、債権者Cが二番抵当権(債権額 1,200 万円)、債権者Dが三番抵当権(債権額 2,000 万円)をそれぞれ有しているが、BがDの利益のため、Aの承諾を得て抵当権の順位を放棄した。甲土地の競売に基づく売却代金が 2,400 万円であった場合、Bの受ける配当額として、民法の規定によれば、正しいものはどれか。
- 【問9】Aを貸主、Bを借主として甲建物の賃貸借契約が令和 5年7月1日に締結された場合の甲建物の修繕に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、誤っているものはどれか。
- 【問8】未成年者Aが、法定代理人Bの同意を得ずに、Cから甲建物を買い受ける契約(以下この問において「本件売買契約」という。)を締結した場合における次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。なお、Aに処分を許された財産はなく、Aは、営業を許されてはいないものとする。
- 【問7】甲建物を所有するAが死亡し、Aの配偶者Bが甲建物の配偶者居住権を、Aの子Cが甲建物の所有権をそれぞれ取得する旨の遺産分割協議が成立した場合に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。
- 【問6】A所有の甲土地について、Bが所有の意思をもって平穏にかつ公然と時効取得に必要な期間占有を継続した場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはいくつあるか。
- 【問5】従来の住所又は居所を去った者(以下この問において「不在者」という。)の財産の管理に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。なお、この問において「管理人」とは、不在者の財産の管理人をいうものとする。
- 【問4】AがBに対して貸金債権である甲債権を、BがAに対して貸金債権である乙債権をそれぞれ有している場合において、民法の規定及び判例によれば、次のアからエまでの記述のうち、Aが一方的な意思表示により甲債権と乙債権とを対当額にて相殺できないものを全て掲げたものは、次の 1 から 4 のうちどれか。なお、いずれの債権も相殺を禁止し又は制限する旨の意思表示はされていないものとする。
- 【問3】Aを注文者、Bを請負人として、A所有の建物に対して独立性を有さずその構成部分となる増築部分の工事請負契約を締結し、Bは 3 か月間で増築工事を終了させた。この場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。なお、この問において「契約不適合」とは品質に関して契約の内容に適合しないことをいい、当該請負契約には契約不適合責任に関する特約は定められていなかったものとする。
- 【問2】相隣関係に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。
- 【問1】次の 1 から 4 までの記述のうち、民法の規定、判例及び下記判決文によれば、誤っているものはどれか。 (判決文) 遺産は、相続人が数人あるときは、相続開始から遺産分割までの間、共同相続人の共有に属するものであるから、この間に遺産である賃貸不動産を使用管理した結果生ずる金銭債権たる賃料債権は、遺産とは別個の財産というべきであって、各共同相続人がその相続分に応じて分割単独債権として確定的に取得するものと解するのが相当である。
- カテゴリー: 令和4年(2022)
- 【問50】建築物の構造に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
- 【問49】土地に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
- 【問48】次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 【問47】宅地建物取引業者が行う広告に関する次の記述のうち、不当景品類及び不当表示防止法(不動産の表示に関する公正競争規約を含む。)の規定によれば、正しいものはどれか。
- 【問46】独立行政法人住宅金融支援機構(以下この間において「機構」という。)に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- 【問45】特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律に基づく住宅販売瑕疵担保保証金の供託又は住宅販売瑕疵担保責任保険契約の締結に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 【問44】宅地建物取引業法(以下この間において「法」という。) 第37条の規定により交付すべき書面(以下この間において「37条書面」という。)に関する次の記述のうち、宅地建物取引業者Aが法の規定に違反するものはどれか。
- 【問43】宅地建物取引業者Aが、自ら売主として行う売買契約に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、誤っているものはどれか。なお、買主は宅地建物取引業者ではないものとする。
- 【問42】宅地建物取引業者Aが、BからB所有の宅地の売却を依頼され、Bと専属専任媒介契約(以下この問において「本件媒介契約」という。)を締結した場合に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。
- 【問41】営業保証金及び宅地建物取引業保証協会(以下この間において「保証協会」という。)に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、誤っているものはいくつあるか。
- 【問40】建物の貸借の媒介を行う宅地建物取引業者が、その取引の相手方(宅地建物取引業者を除く。)に対して、次のアからエの発言に続けて宅地建物取引業法第35条の規定に基づく重要事項の説明を行った場合のうち、宅地建物取引業法の規定に違反しないものはいくつあるか。
- 【問39】宅地建物取引業保証協会(以下この間において「保証協会」という。)に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。
- 【問38】宅地建物取引業者が自ら売主となる宅地の売買契約について、買受けの申込みを喫茶店で行った場合における宅地建物取引業法第37条の2の規定に基づくいわゆるクーリング・オフに関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 【問37】宅地建物取引業者Aがその業務に関して行う広告に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この間において「法」という。)の規定によれば、正しいものはいくつあるか。
- 【問36】宅地建物取引業者が行う宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。なお、説明の相手方は宅地建物取引業者ではないものとする。
- 【問35】次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この間において「法」という。)の規定によれば、正しいものはどれか。
- 【問34】宅地建物取引業者が建物の売買の媒介の際に行う宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。なお、説明の相手方は宅地建物取引業者ではないものとする。
- 【問33】宅地建物取引士に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはいくつあるか。
- 【問32】宅地建物取引業法第37条の規定により交付すべき書面(以下この間において「37条書面」という。)に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- 【問31】宅地建物取引業者Aが、BからB所有の土地付建物の売却について媒介の依頼を受けた場合における次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この間において「法」という。)の規定によれば、正しいものはどれか。
- 【問30】次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この間において「法」という。)及び犯罪による収益の移転防止に関する法律の規定によれば、正しいものはいくつあるか。
- 【問29】宅地建物取引士に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、誤っているものはどれか。
- 【問28】宅地建物取引業者が行う宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 【問27】宅地建物取引業者A(消費税課税事業者)が受け取ることができる報酬についての次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。
- 【問26】宅地建物取引業法第3条第1項に規定する事務所(以下この間において「事務所」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 【問25】地価公示法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- 【問24】固定資産税に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 【問23】印紙税に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。なお、以下の覚書又は契約書はいずれも書面により作成されたものとする。
- 【問22】国土利用計画法第23条の届出 (以下この問において「事後届出」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。なお、この間において「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市にあってはその長をいうものとする。
- 【問21】農地に関する次の記述のうち、農地法(以下この間において「法」という。)の規定によれば、正しいものはどれか。
- 【問20】次の記述のうち、土地区画整理法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。
- 【問19】宅地造成等規制法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。なお、この間において「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市及び施行時特例市にあってはその長をいうものとする。
- 【問18】次の記述のうち、建築基準法(以下この間において「法」という。)の規定によれば、正しいものはどれか。
- 【問17】建築基準法(以下この間において「法」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 【問16】都市計画法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。ただし、この間において条例による特別の定めはないものとし、「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市及び施行時特例市にあってはその長をいうものとする。
- 【問15】都市計画法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- 【問14】不動産の登記に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- 【問13】建物の区分所有等に関する法律(以下この間において「法」という。)に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- 【問12】Aは、B所有の甲建物(床面積 100m²)につき、居住を目的として、期間2年、賃料月額10万円と定めた賃貸借契約(以下この問において「本件契約」という。)をBと締結してその日に引渡しを受けた。この場合における次の記述のうち、民法及び借地借家法の規定並びに判例によれば、誤っているものはどれか。
- 【問11】建物の所有を目的とする土地の賃貸借契約(定期借地権及び一時使用目的の借地権となる契約を除く。)に関する次の記述のうち、借地借家法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。
- 【問10】AはBに対し、自己所有の甲土地を売却し、代金と引換えにBに甲土地を引き渡したが、その後にCに対しても甲土地を売却し、代金と引換えにCに甲土地の所有権登記を移転した。この場合におけるBによる甲土地の所有権の時効取得に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。
- 【問9】辞任に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはいくつあるか。
- 【問8】AがB所有の甲土地を建物所有目的でなく利用するための権原が、①地上権である場合と②賃借権である場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。なお、AもBも対抗要件を備えているものとする。
- 【問7】不在者Aが、家庭裁判所から失踪宣告を受けた。Aを単独相続したBは相続財産である甲土地をCに売却(以下この間において「本件売買契約」という。)して登記も移転したが、その後、生存していたAの請求によって当該失踪宣告が取り消された。本件売買契約当時に、Aの生存について、(ア) Bが善意でCが善意、(イ)Bが悪意でCが善意、(ウ) Bが善意でCが悪意、(エ) Bが悪意でCが悪意、の4つの場合があり得るが、これらのうち、民法の規定及び判例によれば、Cが本件売買契約に基づき取得した甲土地の所有権をAに対抗できる場合を全て掲げたものとして正しいものはどれか。
- 【問6】Aを貸主、Bを借主として、A所有の甲土地につき、資材置場とする目的で期間を2年として、AB間で、①賃貸借契約を締結した場合と、②使用貸借契約を締結した場合に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。
- 【問5】期間の計算に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。なお、明記された日付は、日曜日、国民の祝日に関する法律に規定する休日その他の休日には当たらないものとする。
- 【問4】A所有の甲土地にBのCに対する債務を担保するためにCの抵当権(以下この問において「本件抵当権」という。)が設定され、その旨の登記がなされた場合に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。
- 【問3】制限行為能力者に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。
- 【問2】相続に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、誤っているものはどれか。
- 【問1】次の1から4までの記述のうち、民法の規定、判例及び下記判決文によれば、正しいものはどれか?
- カテゴリー: 令和3年(2021)12月
- 【問50】建物の構造に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
- 【問49】土地に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
- 【問48】次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 【問47】宅地建物取引業者が行う広告に関する次の記述のうち、不当景品類及び不当表示防止法(不動産の表示に関する公正競争規約を含む。)の規定によれば、正しいものはどれか。
- 【問46】独立行政法人住宅金融支援機構(以下この問において「機構」という。)に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- 【問45】宅地建物取引業者Aが、自ら売主として宅地建物取引業者ではない買主Bに新築住宅を販売する場合における次の記述のうち、特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律の規定によれば、正しいものはどれか。
- 【問44】宅地建物取引業者が行う宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明についての次の記述のうち、正しいものはいくつあるか。なお、説明の相手方は宅地建物取引業者ではないものとする。
- 【問43】宅地建物取引業者Aが、自ら売主として、宅地建物取引業者ではない法人B又は宅地建物取引業者ではない個人Cをそれぞれ買主とする土地付建物の売買契約を締結する場合において、宅地建物取引業法第37条の2の規定に基づくいわゆるクーリング・オフに関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。なお、この間において、買主は本件売買契約に係る代金の全部を支払ってはおらず、かつ、土地付建物の引渡しを受けていないものとする。
- 【問42】宅地建物取引業者が媒介により既存建物の貸借の契約を成立させた場合に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法第37条の規定により当該貸借の契約当事者に対して交付すべき書面に記載しなければならない事項はいくつあるか。
- 【問41】宅地建物取引士に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、誤っているものはどれか。
- 【問40】宅地建物取引業法第37条の規定により交付すべき書面(以下この間において「37条書面」という。)についての宅地建物取引業者Aの義務に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 【問39】宅地建物取引業保証協会(以下この間において「保証協会」という。)に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、誤っているものはどれか。
- 【問38】次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定に違反しないものの組合せとして、正しいものはどれか。なお、この問において「建築確認」とは、建築基準法第6条第1項の確認をいうものとする。
- 【問37】宅地建物取引士に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。なお、この間において「登録」とは、宅地建物取引士の登録をいうものとする。
- 【問36】宅地建物取引業の免許(以下この間において「免許」という。)に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。
- 【問35】宅地建物取引業者が宅地及び建物の売買の媒介を行う場合における宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明及び重要事項説明書の交付に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 【問34】宅地、建物に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。
- 【問33】宅地建物取引業者Aは、BからB所有の宅地の売却について媒介の依頼を受けた。この場合における次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはいくつあるか。なお、この間において「専任媒介契約」とは、専属専任媒介契約ではない専任媒介契約をいう。
- 【問32】宅地建物取引業法第35条の2に規定する供託所等に関する説明についての次の記述のうち、正しいものはどれか。なお、特に断りのない限り、宅地建物取引業者の相手方は宅地建物取引業者ではないものとする。
- 【問31】宅地建物取引業者A(消費税課税事業者)が貸主Bから建物の貸借の代理の依頼を受け、宅地建物取引業者C(消費税課税事業者)が借主Dから媒介の依頼を受け、BとDとの間で賃貸借契約を成立させた場合における次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、誤っているものはいくつあるか。なお、1か月分の借賃は8万円とし、借賃及び権利金(権利設定の対価として支払われる金銭であって返還されないものをいう。)には、消費税等相当額を含まないものとする。
- 【問30】宅地建物取引業者Aがその業務に関して行う広告に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この間において「法」という。)の規定によれば、正しいものはどれか。
- 【問29】次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、誤っているものはどれか。
- 【問28】宅地建物取引業者A(甲県知事免許)に関する監督処分及び罰則に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この間において「法」という。)の規定によれば、正しいものはいくつあるか。
- 【問27】宅地建物取引業者Aが、自ら売主として、宅地建物取引業者ではないBとの間で建物の売買契約を締結する場合における次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。
- 【問26】宅地建物取引業者が宅地建物取引業法第37条の規定により交付すべき書面(以下この間において「37条書面」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 【問25】地価公示法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- 【問24】固定資産税に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 【問23】住宅用家屋の所有権の移転登記に係る登録免許税の税率の軽減措置に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 【問22】国土利用計画法(以下この間において「法」という。) 第23条の届出 (以下この問において「事後届出」という。)及び法第29条の届出に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。なお、この間において「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市にあってはその長をいうものとする。
- 【問21】農地に関する次の記述のうち、農地法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、正しいものはどれか。
- 【問20】土地区画整理法(以下この間において「法」という。)に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- 【問19】宅地造成等規制法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。なお、この間において「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市及び施行時特例市にあってはその長をいうものとする。
- 【問18】次の記述のうち、建築基準法(以下この間において「法」という。)の規定によれば、正しいものはどれか。
- 【問17】建築基準法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- 【問16】都市計画法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。ただし、この問において「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市及び施行時特例市にあってはその長をいうものとする。
- 【問15】都市計画法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 【問14】不動産の登記に関する次の記述のうち、不動産登記法の規定によれば、誤っているものはどれか。
- 【問13】建物の区分所有等に関する法律に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- 【問12】賃貸人Aと賃借人Bとの間で令和3年7月1日に締結した一時使用目的ではない建物賃貸借契約(以下この間において「本件契約」という。)の終了に関する次の記述のうち、民法及び借地借家法の規定並びに判例によれば、正しいものはどれか。
- 【問11】次の記述のうち、借地借家法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。
- 【問10】Aは、Bからの借入金の担保として、A所有の甲建物に第一順位の抵当権(以下この間において「本件抵当権」という。)を設定し、その登記を行った。AC間にCを賃借人とする甲建物の一時使用目的ではない賃貸借契約がある場合に関する次の記述のうち、民法及び借地借家法の規定並びに判例によれば、正しいものはどれか。
- 【問9】AがBに対してA所有の甲建物を令和3年7月1日に①売却した場合と②賃貸した場合についての次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。
- 【問8】AはBに対して、Aが所有する甲土地を1,000万円で売却したい旨の申込みを郵便で令和3年7月1日に発信した(以下この問において「本件申込み」という。)が、本件申込みがBに到達する前にAが死亡した場合における次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。
- 【問7】令和3年7月1日になされた遺言に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、誤っているものはどれか。
- 【問6】不動産に関する物権変動の対抗要件に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。
- 【問5】AがBの代理人として行った行為に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。なお、いずれの行為もBの追認はないものとし、令和3年7月1日以降になされたものとする。
- 【問4】いずれも宅地建物取引業者ではない売主Aと買主Bとの間で令和3年7月1日に締結した売買契約に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。
- 【問3】成年後見人が、成年被後見人を代理して行う次に掲げる法律行為のうち、民法の規定によれば、家庭裁判所の許可を得なければ代理して行うことができないものはどれか。
- 【問2】相隣関係に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、誤っているものはどれか。
- 【問1】次の1から4までの記述のうち、民法の規定、判例及び下記判決文によれば、正しいものはどれか。
- カテゴリー: 令和3年(2021)10月
- 【問50】建物の構造に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
- 【問49】土地に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
- 【問48】次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 【問47】宅地建物取引業者が行う広告に関する次の記述のうち、不当景品類及び不当表示防止法(不動産の表示に関する公正競争規約を含む。)の規定によれば、正しいものはどれか。
- 【問46】独立行政法人住宅金融支援機構(以下この問において「機構」という。)に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- 【問45】宅地建物取引業者Aが、自ら売主として宅地建物取引業者ではない買主Bに新築住宅を販売する場合における次の記述のうち、特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律の規定によれば、正しいものはどれか。
- 【問44】宅地建物取引業者A(消費税課税事業者)が受け取ることができる報酬額についての次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。
- 【問43】宅地建物取引業者の業務に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定に違反するものはいくつあるか。
- 【問42】宅地建物取引業者Aが、自ら売主として宅地建物取引業者ではないBを買主とする土地付建物の売買契約(代金3,200万円)を締結する場合に関する次の記述のうち、民法及び宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。
- 【問41】宅地建物取引業者Aが行う業務に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはいくつあるか。なお、この問において「37条書面」とは、同法第 37条の規定により交付すべき書面をいうものとする。
- 【問40】次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。
- 【問39】宅地建物取引業者Aが、自ら売主として、宅地建物取引業者Bの媒介により、宅地建物取引業者ではないCを買主とするマンションの売買契約を締結した場合における宅地建物取引業法第37条の2の規定に基づくいわゆるクーリング・オフについて告げるときに交付すべき書面(以下この問において「告知書面」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 【問38】宅地建物取引業者Aが、宅地建物取引業者BからB所有の建物の売却を依頼され、Bと一般媒介契約(以下この問において「本件契約」という。)を締結した場合に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定に違反しないものはいくつあるか。
- 【問37】宅地建物取引業法第35条の規定に基づく重要事項の説明及び同法第37条の規定により交付すべき書面(以下この問において「37条書面」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 【問36】宅地建物取引業者が行う宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明に関する次の記述のうち、同法の規定に少なくとも説明しなければならない事項として掲げられていないものはどれか。
- 【問35】宅地建物取引士の登録(以下この問において「登録」という。)及び宅地建物取引士証に関する次の記述のうち、正しいものはいくつあるか。
- 【問34】宅地建物取引業法の規定に基づく営業保証金に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 【問33】宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明における水防法施行規則第11条第1号の規定により市町村(特別区を含む。以下この問において同じ。)の長が提供する図面(以下この問において「水害ハザードマップ」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。なお、説明の相手方は宅地建物取引業者ではないものとする。
- 【問32】宅地建物取引業の免許(以下この問において「免許」という。)に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。なお、いずれの場合も、その行為を業として営むものとする。
- 【問31】宅地建物取引業保証協会(以下この問において「保証協会」という。)に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、誤っているものはどれか。
- 【問30】宅地建物取引業者がその業務に関して行う広告に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはいくつあるか。
- 【問29】次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。
- 【問28】宅地建物取引士の登録(以下この問において「登録」という。)に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。
- 【問27】宅地建物取引業の免許(以下この問において「免許」という。)に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。
- 【問26】宅地建物取引業者Aが、自ら売主として宅地建物取引業者ではない買主Bに対し建物の売却を行う場合における宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 【問25】不動産の鑑定評価に関する次の記述のうち、不動産鑑定評価基準によれば、誤っているものはどれか。
- 【問24】不動産取得税に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 【問23】所得税法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 【問22】国土利用計画法第23条の届出(以下この問において「事後届出」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。なお、この間において「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市にあってはその長をいうものとする。
- 【問21】農地に関する次の記述のうち、農地法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、誤っているものはどれか。
- 【問20】土地区画整理法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- 【問19】宅地造成等規制法(以下この間において「法」という。)に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。なお、この問において「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市及び施行時特例市にあってはその長をいうものとする。
- 【問18】次の記述のうち、建築基準法の規定によれば、誤っているものはどれか。
- 【問17】建築基準法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 【問16】都市計画法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。ただし、許可を要する開発行為の面積については、条例による定めはないものとし、この問において「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市及び施行時特例市にあってはその長をいうものとする。
- 【問15】都市計画法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- 【問14】不動産の登記に関する次の記述のうち、不動産登記法の規定によれば、正しいものはどれか。
- 【問13】建物の区分所有等に関する法律(以下この問において「法」という。)に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- 【問12】Aを賃貸人、Bを賃借人とする甲建物の賃貸借契約(以下この問において「本件契約」という。)が令和3年7月1日に締結された場合に関する次の記述のうち、民法及び借地借家法の規定並びに判例によれば、正しいものはどれか。
- 【問11】Aは、所有している甲土地につき、Bとの間で建物所有を目的とする賃貸借契約(以下この問において「借地契約」という。)を締結する予定であるが、期間が満了した時点で、確実に借地契約が終了するようにしたい。この場合に関する次の記述のうち、借地借家法の規定によれば、誤っているものはどれか。
- 【問10】AとBとの間で、Aを売主、Bを買主とする、等価値の美術品甲又は乙のいずれか選択によって定められる美術品の売買契約(以下この問において「本件契約」という。)が令和3年7月1日に締結された場合に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。
- 【問9】Aには死亡した夫Bとの間に子Cがおり、Dには離婚した前妻Eとの間に子F及び子Gがいる。Fの親権はEが有し、Gの親権はDが有している。AとDが婚姻した後にDが令和3年7月1日に死亡した場合における法定相続分として、民法の規定によれば、正しいものはどれか。
- 【問8】Aが1人で居住する甲建物の保存に瑕疵があったため、令和3年7月1日に甲建物の壁が崩れて通行人Bがケガをした場合(以下この問において「本件事故」という。)における次の記述のうち、民法の規定によれば、誤っているものはどれか。
- 【問7】Aを売主、Bを買主として、A所有の甲自動車を50万円で売却する契約(以下この問において「本件契約」という。)が令和3年7月1日に締結された場合に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、誤っているものはどれか。
- 【問6】売買代金債権(以下この問において「債権」という。)の譲渡(令和3年7月1日に譲渡契約が行われたもの)に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、誤っているものはどれか。
- 【問5】次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。
- 【問4】被相続人の配偶者Bが、A所有の建物に相続開始の時に居住していたため、遺産分割協議によって配偶者居住権を取得した場合に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。
- 【問3】個人として事業を営むAが死亡した場合に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、誤っているものはいくつあるか。なお、いずれの契約も令和3年7月1日付けで締結されたものとする。
- 【問2】債務者A、B、Cの3名が、令和3年7月1日に、内部的な負担部分の割合は等しいものとして合意した上で、債権者Dに対して300万円の連帯債務を負った場合に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、誤っているものはどれか。
- 【問1】次の1から4までの記述のうち、民法の規定、判例及び下記判決文によれば、正しいものはどれか。
- カテゴリー: 令和2年(2020)12月
- 【問50】建築物の構造に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
- 【問49】土地に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
- 【問48】次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 【問47】宅地建物取引業者が行う広告に関する次の記述のうち、不当景品類及び不当表示防止法(不動産の表示に関する公正競争規約を含む。)の規定によれば、正しいものはどれか。
- 【問46】独立行政法人住宅金融支援機構(以下この問において「機構」という。)に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- 【問45】宅地建物取引業者Aが自ら売主として、宅地建物取引業者ではない買主Bに新築住宅を販売する場合における次の記述のうち、特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律によれば、正しいものはどれか。
- 【問44】宅地建物取引業法に関する次の記述のうち、正しいものはいくつあるか。
- 【問43】宅地建物取引業法に規定する宅地建物取引士及びその登録(以下この問において「登録」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 【問42】宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。なお、説明の相手方は宅地建物取引業者ではないものとする。
- 【問41】宅地建物取引業法第49条に規定する帳簿に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 【問40】宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)に規定する業務に関する禁止事項についての次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 【問39】宅地建物取引業者Aが、自ら売主として宅地建物取引業者ではない買主Bとの間で締結した宅地の売買契約について、Bが宅地建物取引業法第37条の2の規定に基づき、いわゆるクーリング・オフによる契約の解除をする場合における次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- 【問38】宅地建物取引士に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法及び民法の規定によれば、正しいものはいくつあるか。
- 【問37】宅地建物取引業法第37条の規定により交付すべき書面(以下この間において「37条書面」という。)に関する次の記述のうち、同法の規定によれば、正しいものはどれか。
- 【問36】宅地建物取引業者の守秘義務に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、正しいものはどれか。
- 【問35】宅地建物取引業者Aが行う媒介業務に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはいくつあるか。なお、この間において「37条書面」とは、同法第37条の規定により交付すべき書面をいうものとする。
- 【問34】宅地建物取引業者(消費税課税事業者)が受けることができる報酬に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、誤っているものはどれか。
- 【問33】宅地建物取引業法に規定する営業保証金に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 【問32】宅地建物取引業者が行う宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明に関する次の記述のうち、正しいものはいくつあるか。なお、説明の相手方は宅地建物取引業者ではないものとする。
- 【問31】宅地建物取引業の免許に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。
- 【問30】宅地建物取引業保証協会(以下この間において「保証協会」という。)に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。
- 【問29】次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。
- 【問28】宅地建物取引業者Aが、BからB所有の宅地の売却について媒介の依頼を受けた場合における次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはいくつあるか。なお、この問において「専任媒介契約」とは、専属専任媒介契約ではない専任媒介契約をいうものとする。
- 【問27】宅地建物取引業者がその業務に関して行う広告に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。
- 【問26】次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。
- 【問25】地価公示法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 【問24】固定資産税に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 【問23】住宅用家屋の所有権の移転登記に係る登録免許税の税率の軽減措置に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 【問22】国土利用計画法第23条の届出(以下この間において「事後届出」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。なお、この問において「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市にあってはその長をいうものとする。
- 【問21】農地に関する次の記述のうち、農地法(以下この間において「法」という。)の規定によれば、正しいものはどれか。
- 【問20】土地区画整理法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 【問19】宅地造成等規制法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- 【問18】次の記述のうち、建築基準法(以下この間において「法」という。)の規定によれば、誤っているものはどれか。
- 【問17】建築基準法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- 【問16】都市計画法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。ただし、許可を要する開発行為の面積については、条例による定めはないものとし、この問において「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市及び施行時特例市にあってはその長をいうものとする。
- 【問15】都市計画法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 【問14】不動産の登記に関する次の記述のうち、不動産登記法の規定によれば、誤っているものはどれか。
- 【問13】建物の区分所有等に関する法律に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- 【問12】賃貸人Aと賃借人Bとの間で令和2年7月1日に締結した居住用建物の賃貸借契約に関する次の記述のうち、民法及び借地借家法の規定並びに判例によれば、誤っているものはどれか。
- 【問11】次の記述のうち、借地借家法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。
- 【問10】不動産の共有に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、誤っているものはどれか。
- 【問9】地役権に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。
- 【問8】1億2,000万円の財産を有するAが死亡した場合の法定相続分についての次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものの組み合わせはどれか。
- 【問7】Aを売主、Bを買主として、令和2年7月1日に甲土地の売買契約(以下この問において「本件契約」という。)が締結された場合における次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。
- 【問6】AはBにA所有の甲建物を令和2年7月1日に賃貸し、BはAの承諾を得てCに適法に甲建物を転貸し、Cが甲建物に居住している場合における次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。
- 【問5】時効に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。なお、時効の対象となる債権の発生原因は、令和2年4月1日以降に生じたものとする。
- 【問4】債務不履行に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。なお、債務は令和2年4月1日以降に生じたものとする。
- 【問3】親族に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。
- 【問2】AがBに対して、A所有の甲土地を売却する代理権を令和2年7月1日に授与した場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。
- 【問1】不法行為(令和2年4月1日以降に行われたもの)に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。
- カテゴリー: 令和2年(2020)10月
- 【問50】建築物の構造に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
- 【問49】土地に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
- 【問48】次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 【問47】宅地建物取引業者が行う広告に関する次の記述のうち、不当景品類及び不当表示防止法(不動産の表示に関する公正競争規約を含む。)の規定によれば、正しいものはどれか。
- 【問46】独立行政法人住宅金融支援機構(以下この問において「機構」という。)に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- 【問45】宅地建物取引業者A(甲県知事免許)が、自ら売主として宅地建物取引業者ではない買主Bに新築住宅を販売する場合における次の記述のうち、特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律の規定によれば、正しいものはどれか。
- 【問44】宅地建物取引業者が行う宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。なお、特に断りのない限り、説明の相手方は宅地建物取引業者ではないものとする。
- 【問43】宅地建物取引業の免許(以下この間において「免許」という。)に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。
- 【問42】宅地建物取引業者Aが、自ら売主として締結する売買契約に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)及び民法の規定によれば、誤っているものはどれか。
- 【問41】宅地建物取引業者が行う宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 【問40】宅地建物取引業者Aが、自ら売主として、宅地建物取引業者ではないBとの間で宅地の売買契約を締結した場合における、宅地建物取引業法第37条の2の規定に基づくいわゆるクーリング・オフに関する次の記述のうち、Bがクーリング・オフにより契約の解除を行うことができるものはいくつあるか。
- 【問39】次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。
- 【問38】宅地建物取引業者Aが、BからB所有の甲住宅の売却に係る媒介の依頼を受けて締結する一般媒介契約に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、正しいものはどれか。
- 【問37】宅地建物取引業者Aが、自ら売主として宅地の売買契約を締結した場合に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはいくつあるか。なお、この問において「37条書面」とは、同法第37条の規定に基づき交付すべき書面をいうものとする。
- 【問36】宅地建物取引業保証協会(以下この問において「保証協会」という。)に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。
- 【問35】宅地建物取引業者A(甲県知事免許)の営業保証金に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。
- 【問34】宅地建物取引士の登録(以下この間において「登録」という。)及び宅地建物取引士証に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。
- 【問33】宅地建物取引業者Aが宅地建物取引業法第37条の規定により交付すべき書面(以下この間において「37条書面」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 【問32】宅地建物取引業者Aが、自ら売主として、宅地建物取引業者ではないBとの間で建物の売買契約を締結する場合における次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この間において「法」という。)の規定によれば、正しいものはどれか。
- 【問31】宅地建物取引業者が行う宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。なお、説明の相手方は宅地建物取引業者ではないものとする。
- 【問30】宅地建物取引業者A及び宅地建物取引業者B(ともに消費税課税事業者)が受領する報酬に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。なお、借賃には消費税等相当額を含まないものとする。
- 【問29】宅地建物取引業者Aが、BからB所有の住宅の売却の媒介を依頼された場合における次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、正しいものはいくつあるか。
- 【問28】宅地建物取引士に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。
- 【問27】宅地建物取引業者がその業務に関して行う広告に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはいくつあるか。
- 【問26】宅地建物取引業の免許(以下この間において「免許」という。)に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。
- 【問25】不動産の鑑定評価に関する次の記述のうち、不動産鑑定評価基準によれば、誤っているものはどれか。
- 【問24】不動産取得税に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 【問23】印紙税に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 【問22】国土利用計画法第23条の届出(以下この問において「事後届出」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 【問21】農地に関する次の記述のうち、農地法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、正しいものはどれか。
- 【問20】土地区画整理組合(以下この問において「組合」という。)に関する次の記述のうち、土地区画整理法の規定によれば、正しいものはどれか。
- 【問19】宅地造成等規制法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。なお、この間において「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市及び施行時特例市にあってはその長をいうものとする。
- 【問18】建築基準法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 【問17】建築基準法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 【問16】都市計画法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。なお、この間において「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市及び施行時特例市にあってはその長をいうものとする。
- 【問15】都市計画法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 【問14】不動産の登記に関する次の記述のうち、不動産登記法の規定によれば、正しいものはどれか。
- 【問13】建物の区分所有等に関する法律に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 【問12】AとBとの間でA所有の甲建物をBに対して、居住の用を目的として、期間2年、賃料月額10万円で賃貸する旨の賃貸借契約(以下この問において「本件契約」という。)を締結し、Bが甲建物の引渡しを受けた場合に関する次の記述のうち、民法及び借地借家法の規定並びに判例によれば、誤っているものはどれか。
- 【問11】A所有の甲土地につき、令和2年7月1日にBとの間で居住の用に供する建物の所有を目的として存続期間30年の約定で賃貸借契約(以下この間において「本件契約」という。)が締結された場合に関する次の記述のうち、民法及び借地借家法の規定並びに判例によれば、正しいものはどれか。
- 【問10】Aが甲土地を所有している場合の時効に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。
- 【問9】Aがその所有する甲建物について、Bとの間で、①Aを売主、Bを買主とする売買契約を締結した場合と、②Aを贈与者、Bを受贈者とする負担付贈与契約を締結した場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。なお、これらの契約は、令和2年7月1日に締結され、担保責任に関する特約はないものとする。
- 【問8】相続(令和2年7月1日に相続の開始があったもの)に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、誤っているものはどれか。
- 【問7】保証に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。なお、保証契約は令和2年4月1日以降に締結されたものとする。
- 【問6】AとBとの間で令和2年7月1日に締結された売買契約に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、売買契約締結後、AがBに対し、錯誤による取消しができるものはどれか。
- 【問5】AとBとの間で令和2年7月1日に締結された委任契約において、委任者Aが受任者Bに対して報酬を支払うこととされていた場合に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。
- 【問4】建物の賃貸借契約が期間満了により終了した場合における次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。なお、賃貸借契約は、令和2年7月1日付けで締結され、原状回復義務について特段の合意はないものとする。
- 【問3】次の1から4までの契約に関する記述のうち、民法の規定及び下記判決文によれば、誤っているものはどれか。なお、これらの契約は令和2年4月1日以降に締結されたものとする。
- 【問2】令和2年7月1日に下記ケース①及びケース②の保証契約を締結した場合に関する次の1から4までの記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。
- 【問1】Aが購入した甲土地が他の土地に囲まれて公道に通じない土地であった場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。
- カテゴリー: 令和元年(2019)
- 【問50】建築物の構造に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
- 【問49】土地に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
- 【問48】次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 【問47】宅地建物取引業者が行う広告に関する次の記述のうち、不当景品類及び不当表示(不動産の表示に関する公正競争規約を含む。)の規定によれば、正しいものはどれか。
- 【問46】独立行政法人住宅金融支援機構(以下この問において「機構」という。)に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- 【問45】特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律に基づく住宅販売瑕疵担保保証金の供託又は住宅販売瑕疵担保責任保険契約の締結に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- 【問44】宅地建物取引業法に規定する宅地建物取引士資格登録(以下この問において「登録」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 【問43】宅地建物取引業の免許(以下この問において「免許」という。)に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。
- 【問42】宅地建物取引業法第2条第1号に規定する宅地に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- 【問41】宅地建物取引業者が行う宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明(以下この問において「重要事項説明」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。なお、説明の相手方は宅地建物取引業者ではないものとする。
- 【問40】次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、誤っているものはどれか。
- 【問39】宅地建物取引業者が行う宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。なお、説明の相手方は宅地建物取引業者ではないものとする。
- 【問38】宅地建物取引業者Aが、自ら売主として、宅地建物取引業者ではないBとの間で宅地の売買契約を締結した場合における、宅地建物取引業法第37条の2の規定に基づくいわゆるクーリング・オフに関する次の記述のうち、誤っているものはいくつあるか。
- 【問37】宅地建物取引業者Aが、自ら売主として、宅地建物取引業者ではないBとの間で締結する建築工事完了前のマンション(代金3,000万円)の売買契約に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、正しいものはどれか。
- 【問36】宅地建物取引業者Aが宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)第37条の規定により交付すべき書面(以下この問において「37条書面」という。)に関する次の記述のうち、法の規定によれば、正しいものはいくつあるか。
- 【問35】宅地建物取引業者Aが行う業務に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定に違反しないものはどれか。
- 【問34】宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)第37条の規定により交付すべき書面(以下この問において「37条書面」という。)に関する次の記述のうち、法の規定によれば、正しいものはどれか。
- 【問33】宅地建物取引業保証協会(以下この問において「保証協会」という。)に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。
- 【問32】宅地建物取引業者A(消費税課税事業者)が受け取ることのできる報酬額に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、誤っているものはどれか。なお、この問において報酬額に含まれる消費税等相当額は税率8%で計算するものとする。
- 【問31】宅地建物取引業者Aが、BからB所有の既存のマンションの売却に係る媒介を依頼され、Bと専任媒介契約(専属専任媒介契約ではないものとする。)を締結した。この場合における次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはいくつあるか。
- 【問30】宅地建物取引業者が行う広告に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定に違反するものはいくつあるか。
- 【問29】宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定に基づく監督処分及び罰則に関する次の記述のうち、正しいものはいくつあるか。
- 【問28】宅地建物取引業者が建物の貸借の媒介を行う場合における宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。なお、説明の相手方は宅地建物取引業者ではないものとする。
- 【問27】宅地建物取引業法に関する次の記述のうち、正しいものはいくつあるか。なお、取引の相手方は宅地建物取引業者ではないものとする。
- 【問26】宅地建物取引業法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 【問25】地価公示法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 【問24】固定資産税に関する次の記述のうち、地方税法の規定によれば、正しいものはどれか。
- 【問23】個人が令和元年(平成31年)中に平成31年1月1日において所有期間が10年を超える居住用財産を譲渡した場合のその譲渡に係る譲渡所得の課税に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- 【問22】国土利用計画法第23条の届出(以下この問において「事後届出」とする次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 【問21】農地に関する次の記述のうち、農地法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、正しいものはどれか。
- 【問20】土地区画整理法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- 【問19】宅地造成等規制法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。なお、この問において「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市及び施行時特例市にあってはその長をいうものとする。
- 【問18】建築基準法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 【問17】建築基準法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- 【問16】都市計画法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。ただし、許可を要する開発行為の面積については、条例による定めはないものとし、この問において「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市及び施行時特例市にあってはその長をいうものとする。
- 【問15】都市計画法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- 【問14】不動産の登記に関する次の記述のうち、不動産登記法の規定によれば、誤っているものはどれか。
- 【問13】建物の区分所有等に関する法律(以下この問において「法」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 【問12】AがBに対し、A所有の甲建物を3年間賃貸する旨の契約をした場合における次の記述のうち、民法及び借地借家法の規定によれば、正しいものはどれか(借地借家法第39条に定める取壊し予定の建物の賃貸借及び同法第40条に定める一時使用目的の建物の賃貸借は考慮しないものとする。)。
- 【問11】甲土地につき、期間を50年と定めて賃貸借契約を締結しようとする場合(以下「ケース①」という。)と、期間を15年と定めて賃貸借契約を締結しようとする場合(以下「ケース②」という。)に関する次の記述のうち、民法及び借地借家法の規定によれば、正しいものはどれか。
- 【問10】債務者Aが所有する甲土地には、債権者Bが一番抵当権(債権額2,000万円)、債権者Cが二番抵当権(債権額2,400万円)、債権者Dが三番抵当権(債権額3,000万円)をそれぞれ有しているが、BはDの利益のために抵当権の順位を譲渡した。甲土地の競売に基づく売却代金が6,000万円であった場合、Bの受ける配当額として、民法の規定によれば、正しいものはどれか。
- 【問9】AがBに対して金銭の支払を求めて訴えを提起した場合の時効の中断に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。
- 【問8】Aを注文者、Bを請負人とする請負契約(以下「本件契約」という。)が締結された場合における次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。
- 【問7】Aを売主、Bを買主として甲建物の売買契約が締結された場合におけるBのAに対する代金債務(以下「本件代金債務」という。)に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。
- 【問6】遺産分割に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。
- 【問5】次の1から4までの記述のうち、民法の規定及び判例並びに下記判決文によれば、誤っているものはどれか。
- 【問4】不法行為に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。
- 【問3】事業者ではないAが所有し居住している建物につきAB間で売買契約を締結するかしに当たり、Aは建物引渡しから3か月に限り瑕疵担保責任を負う旨の特約を付けたが、売買契約締結時点において当該建物の構造耐力上主要な部分に瑕疵が存在しており、Aはそのことを知っていたがBに告げず、Bはそのことを知らなかった。この場合に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。
- 【問2】AがBに甲土地を売却し、Bが所有権移転登記を備えた場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。
- 【問1】Aは、Aが所有している甲土地をBに売却した。この場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。
- カテゴリー: 平成30年(2018)
- 【問50】建築物の構造に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
- 【問49】土地に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
- 【問48】次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 【問47】宅地建物取引業者が行う広告に関する次の記述のうち、不当景品類及び不当表示防止法(不動産の表示に関する公正競争規約を含む。)の規定によれば、正しいものはどれか。
- 【問46】独立行政法人住宅金融支援機構(以下この問において「機構」という。)に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- 【問45】特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律に基づく住宅販売瑕疵担保保証金の供託又は住宅販売瑕疵担保責任保険契約の締結に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 【問44】宅地建物取引業保証協会(以下この問において「保証協会」という。)のある宅地建物取引業者Aに関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。
- 【問43】宅地建物取引業法に規定する営業保証金に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 【問42】次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この間において「法」という。)の規定によれば、正しいものはどれか。
- 【問41】次の記述のうち、宅地建物取引業の免許を要する業務が含まれるものはどれか。
- 【問40】宅地建物取引業者Aが行う業務に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定に違反するものはいくつあるか。
- 【問39】宅地建物取引業者が建物の貸借の媒介を行う場合における宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)第35条に規定する重要事項の説明に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。なお、特に断りのない限り、当該建物を借りようとする者は宅地建物取引業者ではないものとする。
- 【問38】宅地建物取引業者である売主は、宅地建物取引業者ではない買主との間で、戸建住宅の売買契約(所有権の登記は当該住宅の引渡し時に行うものとする。)を締結した。この場合における宅地建物取引業法第41条又は第41条の2の規定に基づく手付金等の保全措置(以下この間において「保全措置」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 【問37】宅地建物取引業者である売主Aが、宅地建物取引業者Bの媒介により宅地建物取引業者ではない買主Cと新築マンションの売買契約を締結した場合において、宅地建物取引業法第37条の2の規定に基づくいわゆるクーリング・オフに関する次の記述のうち、正しいものはいくつあるか。
- 【問36】宅地建物取引業の免許(以下この問において「免許」という。)に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。
- 【問35】宅地建物取引業者間の取引における宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明及び重要事項を記載した書面(以下この問において「重要事項説明書」という。)の交付に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 【問34】宅地建物取引業者が媒介により既存建物の貸借の契約を成立させた場合、宅地建物取引業法第37条の規定により、当該貸借の契約当事者に対して交付すべき書面に必ず記載しなければならない事項の組合せはどれか。
- 【問33】宅地建物取引業者Aは、Bから、Bが所有し居住している甲住宅の売却について媒介の依頼を受けた。この場合における次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、正しいものはどれか。
- 【問32】次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。
- 【問31】宅地建物取引業者A(消費税課税事業者)が受け取ることのできる報酬の上限額に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。
- 【問30】宅地建物取引業者A(消費税課税事業者)は、Bが所有する建物について、B及びCから媒介の依頼を受け、Bを貸主、Cを借主とし、1か月分の借賃を10万円(消費税等相当額を含まない。)、CからBに支払われる権利金(権利設定の対価として支払われる金銭であって返還されないものであり、消費税等相当額を含まない。)を150万円とする定期建物賃貸借契約を成立させた。この場合における次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。
- 【問29】Aは、Bとの間で、Aが所有する建物を代金2,000万円で売却する売買契約(以下この間において「本件契約」という。)を締結した。この場合における次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定に違反しないものはどれか。
- 【問28】次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、正しいものはいくつあるか。
- 【問27】宅地建物取引業者Aは、Bが所有し、居住している甲住宅の売却の媒介を、また、宅地建物取引業者Cは、Dから既存住宅の購入の媒介を依頼され、それぞれ媒介契約を締結した。その後、B及びDは、それぞれA及びCの媒介により、甲住宅の売買契約(以下この間において「本件契約」という。)を締結した。この場合における次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、正しいものはどれか。なお、この問において「建物状況調査」とは、法第34条の2第1項第4号に規定する調査をいうものとする。
- 【問26】宅地建物取引業者が行う広告に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、正しいものはどれか。
- 【問25】不動産の鑑定評価に関する次の記述のうち、不動産鑑定評価基準によれば、正しいものはどれか。
- 【問24】不動産取得税に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 【問23】住宅用家屋の所有権の移転登記に係る登録免許税の税率の軽減措置に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 【問22】農地法(以下この間において「法」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 【問21】土地区画整理法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 【問20】宅地造成等規制法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。なお、この間において「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市及び施行時特例市にあってはその長をいうものとする。
- 【問19】建築基準法(以下この問において「法」という。)に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- 【問18】建築基準法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 【問17】都市計画法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。ただし、許可を要する開発行為の面積については、条例による定めはないものとし、この問において「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市及び施行時特例市にあってはその長をいうものとする。
- 【問16】都市計画法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- 【問15】国土利用計画法第23条の届出(以下この問において「事後届出」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 【問14】不動産の登記に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- 【問13】建物の区分所有等に関する法律に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- 【問12】AとBとの間で、Aが所有する甲建物をBが5年間賃借する旨の契約を締結した場合における次の記述のうち、民法及び借地借家法の規定によれば、正しいものはどれか(借地借家法第39条に定める取壊し予定の建物の賃貸借及び同法第40条に定める一時使用目的の建物の賃貸借は考慮しないものとする。)。
- 【問11】AとBとの間で、A所有の甲土地につき建物所有目的で賃貸借契約(以下この問において「本件契約」という。)を締結する場合に関する次の記述のうち、民法及び借地借家法の規定並びに判例によれば、正しいものはどれか。
- 【問10】相続に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。
- 【問9】Aは、平成30年10月1日、A所有の甲土地につき、Bとの間で、代金1,000万円、支払期日を同年12月1日とする売買契約を締結した。この場合の相殺に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。
- 【問8】次の1から4までの記述のうち、民法の規定及び下記判決文によれば、誤っているものはどれか。
- 【問7】債権譲渡に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。
- 【問6】Aが所有する甲土地上にBが乙建物を建築して所有権を登記していたところ、AがBから乙建物を買い取り、その後、Aが甲土地にCのために抵当権を設定し登記した。この場合の法定地上権に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。
- 【問5】Aは、隣人Bの留守中に台風が接近して、屋根の一部が壊れていたB宅に甚大な被害が生じる差し迫ったおそれがあったため、Bからの依頼なくB宅の屋根を修理した。この場合における次の記述のうち、民法の規定によれば、誤っているものはどれか。
- 【問4】時効の援用に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。
- 【問3】AとBとの間で、5か月後に実施される試験(以下この問において「本件試験」という。)にBが合格したときにはA所有の甲建物をBに贈与する旨を書面で約した(以下この問において「本件約定」という。)。この場合における次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。
- 【問2】Aが、所有する甲土地の売却に関する代理権をBに授与し、BがCとの間で、Aを売主、Cを買主とする甲土地の売買契約(以下この問において「本件契約」という。)を締結した場合における次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。
- 【問1】AがBに甲土地を売却した場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。
- カテゴリー: 平成29年(2017)
- 【問50】建物の構造と材料に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
- 【問49】土地に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
- 【問48】次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 【問47】宅地建物取引業者がインターネット不動産情報サイトにおいて行った広告表示に関する次の記述のうち、不当景品類及び不当表示防止法(不動産の表示に関する公正競争規約を含む。)の規定によれば、正しいものはどれか。
- 【問46】独立行政法人住宅金融支援機構(以下この問において「機構」という。)に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- 【問45】宅地建物取引業者Aが自ら売主として、宅地建物取引業者でない買主Bに新築住宅を販売する場合における次の記述のうち、特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律の規定によれば、正しいものはどれか。
- 【問44】宅地建物取引業の免許(以下この問において「免許」という。)に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。
- 【問43】宅地建物取引業者Aが、BからB所有の中古マンションの売却の依頼を受け、Bと専任媒介契約(専属専任媒介契約ではない媒介契約)を締結した場合に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、正しいものはいくつあるか。
- 【問42】宅地建物取引業者が行う広告に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはいくつあるか。
- 【問41】宅地建物取引業者が行う宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。なお、説明の相手方は宅地建物取引業者ではないものとする。
- 【問40】宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)第37条の規定により交付すべき書面(以下この問において「37条書面」という。)に関する次の記述のうち、法の規定に違反しないものはどれか。
- 【問39】営業保証金を供託している宅地建物取引業者Aと宅地建物取引業保証協会(以下この問において「保証協会」という。)の社員である宅地建物取引業者Bに関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはいくつあるか。
- 【問38】宅地建物取引業者Aが、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)第37条の規定により交付すべき書面(以下この問において「37条書面」という。)に関する次の記述のうち、法の規定に違反しないものはどれか。
- 【問37】次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、正しいものはどれか。
- 【問36】次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。なお、この問において「免許」とは、宅地建物取引業の免許をいう。
- 【問35】次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この間において「法」という。)の規定によれば、正しいものはどれか。
- 【問34】次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、誤っているものはどれか。
- 【問33】宅地建物取引業者が行う宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。なお、説明の相手方は宅地建物取引業者ではないものとする。
- 【問32】宅地建物取引業法に規定する営業保証金に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- 【問31】宅地建物取引業者Aが、自ら売主として、宅地建物取引業者でないBとの間でマンション(代金3,000万円)の売買契約を締結しようとする場合における次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この間において「法」という。)の規定によれば、正しいものはいくつあるか。
- 【問30】宅地建物取引業法(以下この間において「法」という。)の規定に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。なお、この間において「登録」とは、宅地建物取引士の登録をいうものとする。
- 【問29】次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、正しいものはどれか。
- 【問28】宅地建物取引業者Aが行う業務に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定に違反しないものはいくつあるか。
- 【問27】宅地建物取引業者Aが、自ら売主として宅地建物取引業者でない買主Bとの間で締結した宅地の売買契約に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法及び民法の規定によれば、正しいものはいくつあるか。
- 【問26】宅地建物取引業者A(消費税課税事業者)は貸主Bから建物の貸借の媒介の依頼を受け、宅地建物取引業者C(消費税課税事業者)は借主Dから建物の貸借の媒介の依頼を受け、BとDの間での賃貸借契約を成立させた。この場合における次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この間において「法」という。)の規定によれば、正しいものはどれか。なお、 1か月分の借賃は9万円(消費税等相当額を含まない。)である。
- 【問25】地価公示法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 【問24】固定資産税に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 【問23】所得税法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 【問22】次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 【問21】土地区画整理法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。なお、この問において「組合」とは、土地区画整理組合をいう。
- 【問20】宅地造成等規制法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。なお、この問において「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市及び施行時特例市にあってはその長をいうものとする。
- 【問19】建築基準法(以下この問において「法」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 【問18】建築基準法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- 【問17】都市計画法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。ただし、許可を要する開発行為の面積について、条例による定めはないものとし、この問において「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市及び施行時特例市にあってはその長をいうものとする。
- 【問16】都市計画法に関する次の記述のうち、正しいものの組合せはどれか。
- 【問15】農地に関する次の記述のうち、農地法(以下この間において「法」という。)の規定によれば、正しいものはどれか。
- 【問14】不動産の登記に関する次の記述のうち、不動産登記法の規定によれば、誤っているものはどれか。
- 【問13】建物の区分所有等に関する法律に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- 【問12】Aが所有する甲建物をBに対して3年間賃貸する旨の契約をした場合における次の記述のうち、借地借家法の規定によれば、正しいものはどれか。
- 【問11】A所有の甲土地につき、平成29年10月1日にBとの間で賃貸借契約(以下「本件契約」という。)が締結された場合に関する次の記述のうち、民法及び借地借家法の規定並びに判例によれば、正しいものはどれか。
- 【問10】①不動産質権と②抵当権に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、誤っているものはどれか。
- 【問9】1億2,000万円の財産を有するAが死亡した。Aには、配偶者はなく、子B、C、Dがおり、Bには子Eが、Cには子Fがいる。Bは相続を放棄した。また、Cは生前のAを強迫して遺言作成を妨害したため、相続人となることができない。この場合における法定相続分に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。
- 【問8】A、B、Cの3人がDに対して900万円の連帯債務を負っている場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。なお、A、B、Cの負担部分は等しいものとする。
- 【問7】請負契約に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。
- 【問6】Aが死亡し、相続人がBとCの2名であった場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。
- 【問5】Aは、中古自動車を売却するため、Bに売買の媒介を依頼し、報酬として売買代金の3%を支払うことを約した。Bの媒介によりAは当該自動車をCに100万円で売却した。この場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。
- 【問4】次の記述のうち、平成29年4月1日現在施行されている民法の条文に規定されているものはどれか。
- 【問3】次の1から4までの記述のうち、民法の規定及び下記判決文によれば、誤っているものはどれか。
- 【問2】所有権の移転又は取得に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。
- 【問1】代理に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。
- カテゴリー: 平成28年(2016)
- 【問50】建築物の構造に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
- 【問49】土地に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
- 【問48】次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 【問47】宅地建物取引業者が行う広告に関する次の記述のうち、不当景品類及び不当表示防止法(不動産の表示に関する公正競争規約を含む。)の規定によれば、正しいものはどれか。
- 【問46】独立行政法人住宅金融支援機構(以下この問において「機構」という。)に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- 【問45】宅地建物取引業者Aが、自ら売主として、宅地建物取引業者でないBに新築住宅を販売する場合における次の記述のうち、特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律の規定によれば、正しいものはどれか。
- 【問44】宅地建物取引業者Aが、自ら売主として、宅地建物取引業者でないBと宅地の売買契約を締結した場合、宅地建物取引業法第37条の2の規定に基づくいわゆるクーリング・オフについてAがBに告げるときに交付すべき書面の内容に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- 【問43】宅地建物取引業者Aが、自ら売主として、宅地建物取引業者でないBと建築工事完了前のマンション(代金3,000万円)の売買契約を締結した場合、宅地建物取引業法第41条の規定に基づく手付金等の保全措置(以下この問において「保全措置」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはいくつあるか。
- 【問42】宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)第37条の規定により交付すべき書面(以下この問において「37条書面」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。なお、Aは宅地建物取引業者(消費税課税事業者)である。
- 【問41】宅地建物取引業者Aが行う業務に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、正しいものはどれか。
- 【問40】宅地建物取引業者A(甲県知事免許)は、甲県に本店と支店を設け、営業保証金として1,000万円の金銭と額面金額500万円の国債証券を供託し、営業している。この場合に関する次の記述のうち宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。
- 【問39】宅地建物取引業者が媒介により区分所有建物の貸借の契約を成立させた場合に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、正しいものはどれか。なお、この問において「重要事項説明書」とは法第35条の規定により交付すべき書面をいい、「37条書面」とは法第37条の規定により交付すべき書面をいうものとする。
- 【問38】宅地建物取引士資格登録(以下この問において「登録」という。)又は宅地建物取引士に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはいくつあるか。
- 【問37】宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定に関する次の記述のうち、正しいものはいくつあるか。
- 【問36】宅地建物取引業者が行う宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明に関する次の記述のうち、正しいものはいくつあるか。
- 【問35】宅地建物取引業の免許(以下この問において「免許」という。)に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。
- 【問34】宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)第47条及び第47条の2に規定されている業務に関する禁止事項に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。なお、Aは宅地建物取引業者である。
- 【問33】宅地建物取引業者が売買等の媒介に関して受けることができる報酬についての次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、誤っているものはいくつあるか。
- 【問32】宅地建物取引業者A(甲県知事免許)がその業務に関して広告を行った場合における次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定に違反しないものはどれか。
- 【問31】宅地建物取引業保証協会(以下この問において「保証協会」という。)の社員である宅地建物取引業者に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。
- 【問30】宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明及び同法第37条の規定により交付すべき書面(以下この問において「37条書面」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 【問29】宅地建物取引業者Aの業務に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定に違反するものの組合せはどれか。
- 【問28】宅地建物取引業者Aが、自ら売主として、宅地建物取引業者でないBとの間でマンション(代金4,000万円)の売買契約を締結した場合に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定に違反するものの組合せはどれか。
- 【問27】宅地建物取引業者Aが、BからB所有の宅地の売却に係る媒介を依頼された場合における次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、正しいものはどれか。なお、この問において一般媒介契約とは、専任媒介契約でない媒介契約をいう。
- 【問26】宅地建物取引業者A(甲県知事免許)に対する監督処分に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、正しいものはどれか。
- 【問25】不動産の鑑定評価に関する次の記述のうち、不動産鑑定評価基準によれば、正しいものはどれか。
- 【問24】不動産取得税に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 【問23】印紙税に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 【問22】農地に関する次の記述のうち、農地法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、正しいものはどれか。
- 【問21】土地区画整理法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- 【問20】宅地造成等規制法(以下この問において「法」という。)に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。なお、この問において「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市及び施行時特例市にあってはその長をいうものとする。
- 【問19】建築基準法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- 【問18】建築基準法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 【問17】都市計画法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。なお、この問において「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市及び施行時特例市にあってはその長をいうものとする。
- 【問16】都市計画法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 【問15】国土利用計画法第23条に規定する届出(以下この問において「事後届出」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 【問14】不動産の登記に関する次の記述のうち、不動産登記法の規定によれば、誤っているものはどれか。
- 【問13】建物の区分所有等に関する法律に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 【問12】AはBと、B所有の甲建物につき、居住を目的として、期間3年、万円と定めて賃貸借契約(以下この問において「本件契約」という。)を締結した。この場合における次の記述のうち、借地借家法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。
- 【問11】Aが居住用の甲建物を所有する目的で、期間30年と定めてBから乙土地を賃借した場合に関する次の記述のうち、借地借家法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。なお、Aは借地権登記を備えていないものとする。
- 【問10】甲建物を所有するAが死亡し、相続人がそれぞれAの子であるB及びCの2名である場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。
- 【問9】次の1から4までの記述のうち、民法の規定及び下記判決文によれば、誤っているものはどれか。
- 【問8】AがBに甲建物を月額10万円で賃貸し、BがAの承諾を得て甲建物をCに適法に月額15万円で転貸している場合における次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。
- 【問7】AがBから賃借する甲建物に、運送会社Cに雇用されているDが居眠り運転するトラックが突っ込んで甲建物の一部が損壊した場合(以下「本件事故」という。)に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはいくつあるか。なお、DはCの業務として運転をしていたものとする。
- 【問6】Aを売主、Bを買主とする甲土地の売買契約(以下この問において「本件契約」という。)が締結された場合の売主の担保責任に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。
- 【問5】Aが、Bに対する債権をCに譲渡した場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。
- 【問4】Aは、A所有の甲土地にBから借り入れた3,000万円の担保として抵当権を設定した。この場合における次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。
- 【問3】AがA所有の甲土地をBに売却した場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。
- 【問2】制限行為能力者に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。
- 【問1】次の記述のうち、民法の条文に規定されているものはどれか。
- カテゴリー: 平成27年(2015)
- 【問50】建物の構造に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
- 【問49】土地に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
- 【問48】次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 【問47】宅地建物取引業者が行う広告に関する次の記述のうち、不当景品類及び不当表示防止法(不動産の表示に関する公正競争規約を含む。)の規定によれば、正しいものはどれか。
- 【問46】独立行政法人住宅金融支援機構(以下この問において「機構」という。)に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- 【問45】特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律に基づく住宅販売瑕疵担保保証金の供託又は住宅販売瑕疵担保責任保険契約の締結に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 【問44】宅地建物取引業者A(甲県知事免許)が乙県内に所在するマンション(100戸)を分譲する場合における次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この間において「法」という。)の規定によれば、正しいものはどれか。
- 【問43】宅地建物取引業法の規定に基づく監督処分等に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- 【問42】営業保証金を供託している宅地建物取引業者Aと宅地建物取引業保証協会(以下この問において「保証協会」という。)の社員である宅地建物取引業者Bに関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。
- 【問41】宅地建物取引業者が売主である新築分譲マンションを訪れた買主Aに対して、当該宅地建物取引業者の従業者Bが行った次の発言内容のうち、宅地建物取引業法の規定に違反しないものはいくつあるか。
- 【問40】宅地建物取引業者Aが、自ら売主として宅地建物取引業者でない買主Bとの間で締結した売買契約に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはいくつあるか。
- 【問39】宅地建物取引業者Aが自ら売主となる売買契約に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、正しいものはどれか。
- 【問38】宅地建物取引業者Aが宅地建物取引業法第37条の規定により交付すべき書面(以下この問において「37条書面」という。)に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはいくつあるか。
- 【問37】次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。なお、この問において「建築確認」とは、建築基準法第6条第1項の確認をいうものとする。
- 【問36】宅地建物取引業者Aが、自ら売主として、宅地建物取引業者でないBとの間で建物(代金2,400万円)の売買契約を締結する場合における次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはいくつあるか。
- 【問35】宅地建物取引業法の規定に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 【問34】宅地建物取引業者Aが、自ら売主として、宅地建物取引業者でないBとの間で建物の売買契約を締結する場合における次の記述のうち、民法及び宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。
- 【問33】宅地建物取引業者A及びB(ともに消費税課税事業者)が受領した報酬に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定に違反するものの組合せはどれか。なお、この問において「消費税等相当額」とは、消費税額及び地方消費税額に相当する金額をいうものとする。
- 【問32】宅地建物取引業者が行う宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明に「関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 【問31】宅地建物取引業者が、宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明を行う場合における次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定に違反するものはいくつあるか。
- 【問30】宅地建物取引業者Aは、Bが所有する宅地の売却を依頼され、専任媒介契約を締結した。この場合における次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定に違反するものはいくつあるか。
- 【問29】宅地建物取引業者が行う宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明及び書面の交付に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 【問28】宅地建物取引業者Aが行う業務に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、正しいものはいくつあるか。
- 【問27】宅地建物取引業の免許(以下この問において「免許」という。)に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、誤っているものはどれか。・
- 【問26】次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、正しいものはいくつあるか。
- 【問25】地価公示法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- 【問24】固定資産税に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 【問23】「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税」に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 【問22】農地に関する次の記述のうち、農地法(以下この問において(以下この問において「法」という。)の規定によれば、正しいものはどれか。
- 【問21】国土利用計画法第23条の事後届出(以下この間において「事後届出」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 【問20】土地区画整理法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- 【問19】宅地造成等規制法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。なお、この問において「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市及び施行時特例市にあってはその長をいうものとする。
- 【問18】建築基準法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- 【問17】建築基準法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- 【問16】都市計画法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 【問15】都市計画法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。なお、この間において「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市及び施行時特例市にあってはその長をいうものとする。
- 【問14】不動産の登記に関する次の記述のうち、不動産登記法の規定によれば、誤っているものはどれか。
- 【問13】建物の区分所有等に関する法律に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 【問12】賃貸人と賃借人との間で、建物につき、期間5年として借地借家法第38条に定める定期借家契約(以下「定期借家契約」という。)を締結する場合と、期間5年として定期借家契約ではない借家契約(以下「普通借家契約」という。)を締結する場合に関する次の記述のうち、民法及び借地借家法の規定によれば、正しいものはどれか。なお、借地借家法第 40条に定める一時使用目的の賃貸借契約は考慮しないものとする。
- 【問11】AがBとの間で、A所有の甲建物について、期間3年、賃料月額10万円と定めた賃貸借契約を締結した場合に関する次の記述のうち、民法及び借地借家法の規定並びに判例によれば、正しいものはどれか。
- 【問10】遺言及び遺留分に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。
- 【問9】土地の転貸借に関する次の1から4までの記述のうち、民法の規定、判例及び下記判決文によれば、誤っているものはどれか。
- 【問8】同時履行の抗弁権に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはいくつあるか。
- 【問7】債務者Aが所有する甲土地には、債権者Bが一番抵当権(債権額2,000万円)、債権者Cが二番抵当権(債権額2,400万円)、債権者Dが三番抵当権(債権額4,000万円)をそれぞれ有しており、Aにはその他に担保権を有しない債権者(債権額2,000万円)がいる。甲土地の競売に基づく売却代金5,400万円を配当する場合に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、誤っているものはどれか。
- 【問6】抵当権に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。
- 【問5】占有に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。
- 【問4】A所有の甲土地を占有しているBによる権利の時効取得に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。
- 【問3】AB間で、Aを貸主、Bを借主として、A所有の甲建物につき、①賃貸借契約を締結した場合と、②使用貸借契約を締結した場合に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、誤っているものはどれか。
- 【問2】Aは、その所有する甲土地を譲渡する意思がないのに、Bと通謀して、Aを売主、Bを買主とする甲土地の仮装の売買契約を締結した。この場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。なお、この問において「善意」又は「悪意」とは、虚偽表示の事実についての善意又は悪意とする。
- 【問1】次の記述のうち、民法の条文に規定されているものはどれか。
- カテゴリー: その他