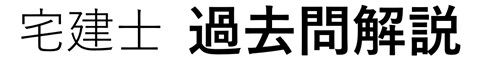令和6年(2024)– category –
-

【問20】土地区画整理法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。なお、この問において、同法第136条の3による大都市等の特例及び条例で定める事務処理の特例は考慮しないものとする。
仮換地が指定された場合においては、従前の宅地について権原に基づき使用し、又は収益することができる者は、仮換地の指定の効力発生の日から換地処分の公告がある日まで、仮換地又は仮換地について仮に使用し、若しくは収益することができる権利の目的... -

【問19】宅地造成及び特定盛土等規制法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。なお、この問において「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市及び中核市にあってはその長をいうものとし、地方自治法に基づく施行時特例市に係る経過措置については考慮しないものとする。
都道府県知事は、基礎調査のために他人の占有する土地に立ち入って測量又は調査を行う必要があるときは、その必要の限度において、当該土地に、自ら立ち入り、又はその命じた者若しくは委任した者に立ち入らせることができ、当該土地の占有者は、正当な... -

【問18】次の記述のうち、建築基準法の規定によれば、正しいものはどれか。
客席部分の床面積の合計が300m2の映画館については、第二種住居地域内において建築することはできないが、準住居地域内においては建築することができる。 特定用途誘導地区内において、都市計画で建築物の高さの最高限度が定められていたとしても、特定行... -

【問17】建築基準法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。なお、建築副主事の確認にあっては、建築基準法に定める大規模建築物以外の建築物に限るものとする。
高さ25mの建築物には、周囲の状況によって安全上支障がない場合を除き、有効に避雷設備を設けなければならない。 特定行政庁は、建築基準法の規定に違反した建築物(国、都道府県又は建築主事を置く市町村の建築物を除く。)の所有者に対して、緊急の必要... -

【問16】都市計画法(以下この問において「法」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。ただし、この問において条例による特別の定めはないものとし、「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市及び施行時特例市にあってはその長をいうものとする。
市街化区域内において行う、医療法に規定する病院を建築するための1,000m2の開発行為については、法第29条に基づく都道府県知事の許可を得る必要がある。 市街化区域内において行う、開発行為を伴わない建築物の建築で、当該建築物の床面積が1,000m2以... -

【問15】都市計画法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
都市計画区域外においても、特に必要があるときは、都市施設に関する都市計画を定めることができる。 準都市計画区域については、用途地域が定められている土地の区域であっても、市街地開発事業に関する都市計画を定めることができない。 用途地域... -

【問14】不動産の登記に関する次の記述のうち、不動産登記法の規定によれば、誤っているものはどれか。
買戻しの特約に関する登記がされている場合において、契約の日から10年を経過したときは、登記権利者は、単独で当該登記の抹消を申請することができる。 不動産の収用による所有権の移転の登記は、起業者が単独で申請することができる。 相続人では... -

【問13】建物の区分所有等に関する法律に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
各共有者の共用部分の持分は、規約に別段の定めがない限り、共有者数で等分することとされている。 規約及び集会の決議は、区分所有者の特定承継人に対しても、その効力を生ずる。 管理者は、集会において、毎年1回一定の時期に、その事務に関する報... -

【問12】賃貸人Aと賃借人Bとが、居住目的で期間を3年として、借地借家法第38条の定期建物賃貸借契約(以下この問において「契約①」という。)を締結した場合と、定期建物賃貸借契約でも一時使用目的の賃貸借契約でもない普通建物賃貸借契約(以下この問において「契約②」という。)を締結した場合とに関する次の記述のうち、借地借家法の規定によれば、正しいものはどれか。
Bが建物の引渡しを受けた後にAが建物をCに売却して建物所有者がCに変わった場合、Bは、契約①の場合ではCに対して賃借人であることを主張できるが、契約②の場合ではCに対して賃借人であることを主張できない。 契約期間中は賃料の改定を行わない... -

【問11】建物の所有を目的とする土地の賃貸借契約(一時使用目的の借地契約を除く。)に関する次の記述のうち、借地借家法の規定によれば、正しいものはどれか。
専ら事業の用に供する建物(居住の用に供するものを除く。)の所有を目的とし、存続期間を20年として借地権を設定する場合、建物買取請求権の規定は適用されず、また、その契約は、公正証書による等書面によってしなければならない。 居住の用に供する...