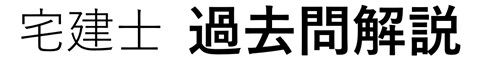令和3年(2021)12月– category –
-

【問26】宅地建物取引業者が宅地建物取引業法第37条の規定により交付すべき書面(以下この間において「37条書面」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
-

【問27】宅地建物取引業者Aが、自ら売主として、宅地建物取引業者ではないBとの間で建物の売買契約を締結する場合における次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。
-

【問28】宅地建物取引業者A(甲県知事免許)に関する監督処分及び罰則に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この間において「法」という。)の規定によれば、正しいものはいくつあるか。
-

【問29】次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、誤っているものはどれか。
-

【問30】宅地建物取引業者Aがその業務に関して行う広告に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この間において「法」という。)の規定によれば、正しいものはどれか。
-

【問31】宅地建物取引業者A(消費税課税事業者)が貸主Bから建物の貸借の代理の依頼を受け、宅地建物取引業者C(消費税課税事業者)が借主Dから媒介の依頼を受け、BとDとの間で賃貸借契約を成立させた場合における次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、誤っているものはいくつあるか。なお、1か月分の借賃は8万円とし、借賃及び権利金(権利設定の対価として支払われる金銭であって返還されないものをいう。)には、消費税等相当額を含まないものとする。
-

【問32】宅地建物取引業法第35条の2に規定する供託所等に関する説明についての次の記述のうち、正しいものはどれか。なお、特に断りのない限り、宅地建物取引業者の相手方は宅地建物取引業者ではないものとする。
-

【問33】宅地建物取引業者Aは、BからB所有の宅地の売却について媒介の依頼を受けた。この場合における次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはいくつあるか。なお、この間において「専任媒介契約」とは、専属専任媒介契約ではない専任媒介契約をいう。
-

【問34】宅地、建物に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。
-

【問35】宅地建物取引業者が宅地及び建物の売買の媒介を行う場合における宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明及び重要事項説明書の交付に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
-

【問36】宅地建物取引業の免許(以下この間において「免許」という。)に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。
-

【問37】宅地建物取引士に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。なお、この間において「登録」とは、宅地建物取引士の登録をいうものとする。
-

【問38】次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定に違反しないものの組合せとして、正しいものはどれか。なお、この問において「建築確認」とは、建築基準法第6条第1項の確認をいうものとする。
-

【問39】宅地建物取引業保証協会(以下この間において「保証協会」という。)に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、誤っているものはどれか。
-

【問40】宅地建物取引業法第37条の規定により交付すべき書面(以下この間において「37条書面」という。)についての宅地建物取引業者Aの義務に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
-

【問41】宅地建物取引士に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、誤っているものはどれか。
-

【問42】宅地建物取引業者が媒介により既存建物の貸借の契約を成立させた場合に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法第37条の規定により当該貸借の契約当事者に対して交付すべき書面に記載しなければならない事項はいくつあるか。
-

【問43】宅地建物取引業者Aが、自ら売主として、宅地建物取引業者ではない法人B又は宅地建物取引業者ではない個人Cをそれぞれ買主とする土地付建物の売買契約を締結する場合において、宅地建物取引業法第37条の2の規定に基づくいわゆるクーリング・オフに関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。なお、この間において、買主は本件売買契約に係る代金の全部を支払ってはおらず、かつ、土地付建物の引渡しを受けていないものとする。
-

【問44】宅地建物取引業者が行う宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明についての次の記述のうち、正しいものはいくつあるか。なお、説明の相手方は宅地建物取引業者ではないものとする。
-

【問45】宅地建物取引業者Aが、自ら売主として宅地建物取引業者ではない買主Bに新築住宅を販売する場合における次の記述のうち、特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律の規定によれば、正しいものはどれか。
-

【問46】独立行政法人住宅金融支援機構(以下この問において「機構」という。)に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
-

【問47】宅地建物取引業者が行う広告に関する次の記述のうち、不当景品類及び不当表示防止法(不動産の表示に関する公正競争規約を含む。)の規定によれば、正しいものはどれか。
-

【問48】次の記述のうち、正しいものはどれか。
-

【問49】土地に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
-

【問50】建物の構造に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
12